TDM業務
TDM(Therapeutic Drug Monitoring)とは、患者さんの薬物血中濃度を測定し、薬物動態解析、検査値、病態を加味して患者さん個々に適した薬物投与設計を行うことです。
当院では、主に薬剤部で薬物血中濃度を測定しており、解析結果は病棟薬剤師と共有しています。病棟薬剤師は、患者さんのところに伺うなどしてさらに情報を収集した上で医師とディスカッションを行い、総合的な薬物治療計画を支援しています。
なお、薬剤部では、化学発光免疫測定法、電気化学発光免疫測定法、高速液体クロマトグラフィー法などの分析手法を用いて薬物血中濃度を測定しています。
薬剤部における測定薬物
神経系に作用する薬
カルバマゼピン、クロザピン、バルプロ酸、フェニトイン、フェノバルビタール、ラモトリギン、リチウム
循環器系に作用する薬
アミオダロン、ジゴキシン
病原微生物に対する薬
アミカシン、ゲンタマイシン、テイコプラニン、トブラマイシン、バンコマイシン、ボリコナゾール
免疫・アレルギーに
作用する薬
シクロスポリン、タクロリムス、ミコフェノール酸モフェチル
呼吸器系に作用する薬
テオフィリン
抗悪性腫瘍薬
イマチニブ、メトトレキサート
(2025年7月現在)

薬剤師による血液検体の前処理

高速液体クロマトグラフィー法を用いた
薬物血中濃度測定
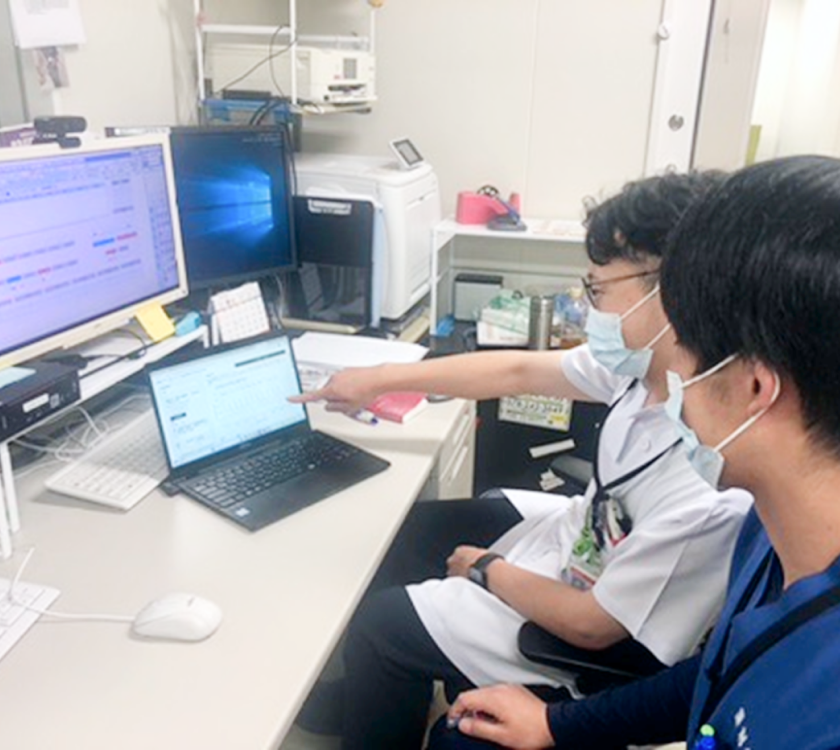
解析ソフトを用いた薬物動態解析



