離乳食初期(5~6ヶ月)に、白身魚、豆腐、などとたんぱく質性食品に慣れたら、卵黄を始めます。
卵黄は固ゆで卵(20分ゆでる)の卵黄のみを耳かき1杯から与え、問題なければ徐々に増やしていきましょう。卵のアレルゲンは加熱によって弱くなるため、十分な加熱調理が必要です。
卵ボーロは製造の工程から白身が含まれている可能性があるため、卵白が食べられることが確認できてから与えるよう注意しましょう。
- 離乳食初期 5~6ヶ月頃
卵黄1さじ→漸増
- 離乳食中期 7~8ヶ月頃
卵黄1個→全卵1/3個
- 離乳食後期 9~11ヶ月頃
全卵1/2個
- 離乳食完了期 12~18ヶ月頃
全卵1/2~2/3個
離乳食中期(7~8ヶ月)に、ヨーグルトや牛乳、塩分の少ないカッテージチーズなどを始めます。牛乳を飲用として摂取する適切な時期は1歳以降なので、この時期は料理に使用し、加熱して与えましょう。
- 離乳食初期 5~6ヶ月頃
育児用ミルク以外は与えません
- 離乳食中期 7~8ヶ月頃
プレーンヨーグルト50~70g
牛乳(料理に使用)50~70ml
カッテージチーズ 大さじ1弱
スライスチーズ 1/3枚
- 離乳食後期 9~11ヶ月頃
プレーンヨーグルト80g
牛乳(料理に使用)80ml
カッテージチーズ 大さじ1.5
スライスチーズ 2/3枚
- 離乳食完了期 12~18ヶ月頃
プレーンヨーグルト100g
牛乳(料理に使用)100ml
カッテージチーズ 大さじ2弱
スライスチーズ 1枚弱
小麦製品は6ヶ月以降に与えましょう。初めは、塩分の含まれない赤ちゃん用のうどんやそうめんが、おすすめです。食パンには卵が含まれる場合もあるので、含まれる商品については卵が摂取できることを確認してから与えるようにしましょう 。
- 離乳食初期 5~6ヶ月頃
つぶしがゆ1さじ~
※小麦製品は6か月以降に1さじ~
- 離乳食中期 7~8ヶ月頃
全粥50~80g
食パン15~20g
うどん(茹)35~55g
そうめん(乾)10~15g
コーンフレーク10~15g
- 離乳食後期 9~11ヶ月頃
全粥90g~軟飯80g
食パン25~35g
うどん(茹)60~90g
そうめん(乾)20~30g
コーンフレーク15~25g
パスタ(乾)15~25g
- 離乳食完了期 12~18ヶ月頃
軟飯90g~ご飯80g
食パン40~50g
うどん(茹)105~130g
そうめん(乾)30~40g
コーンフレーク30~35g
パスタ(乾)30~35g
中華蒸し麺55~70g
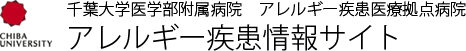
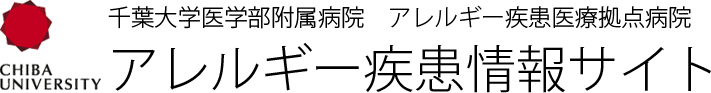
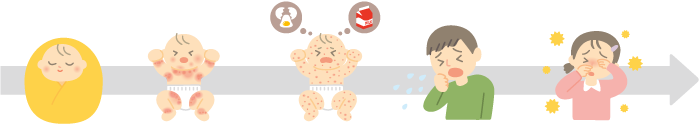
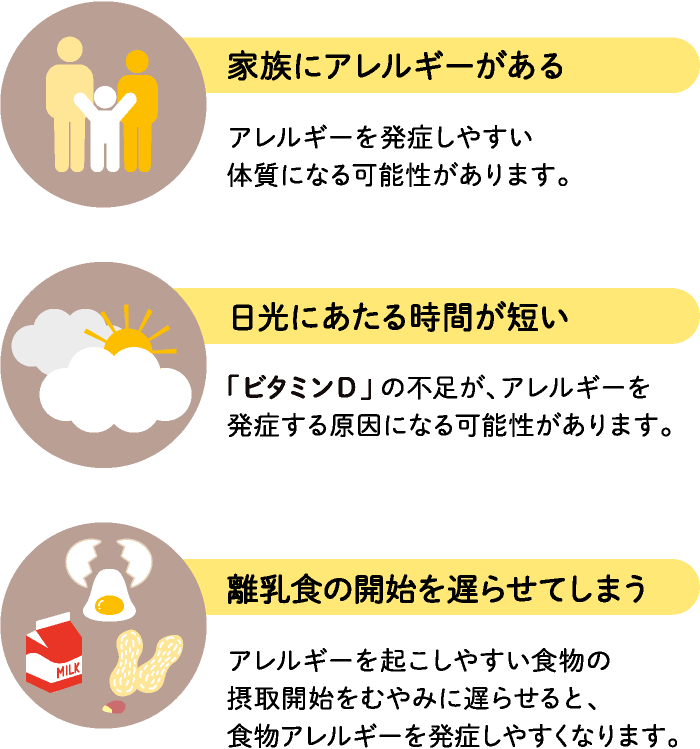
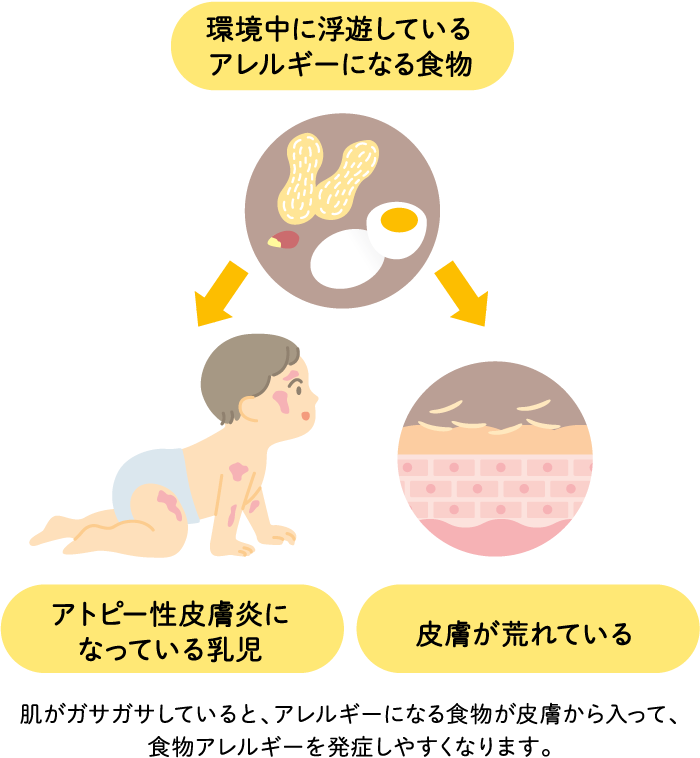
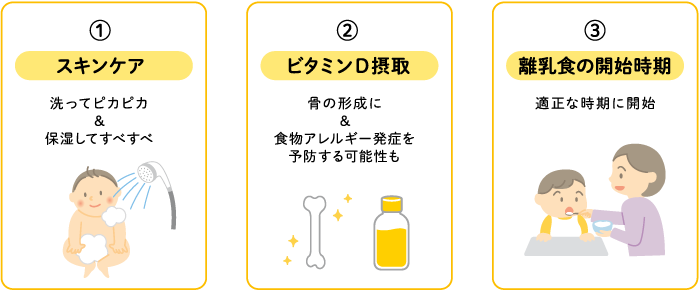
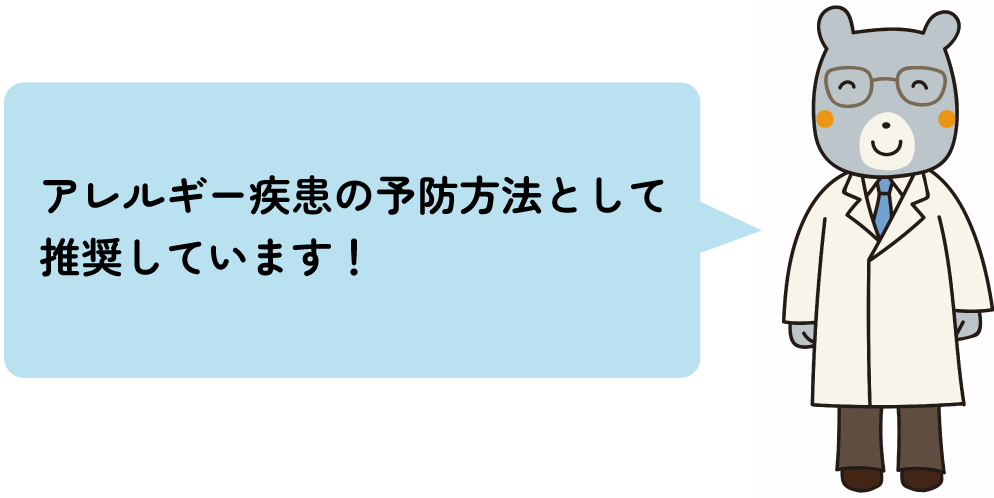
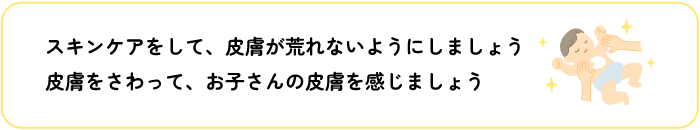
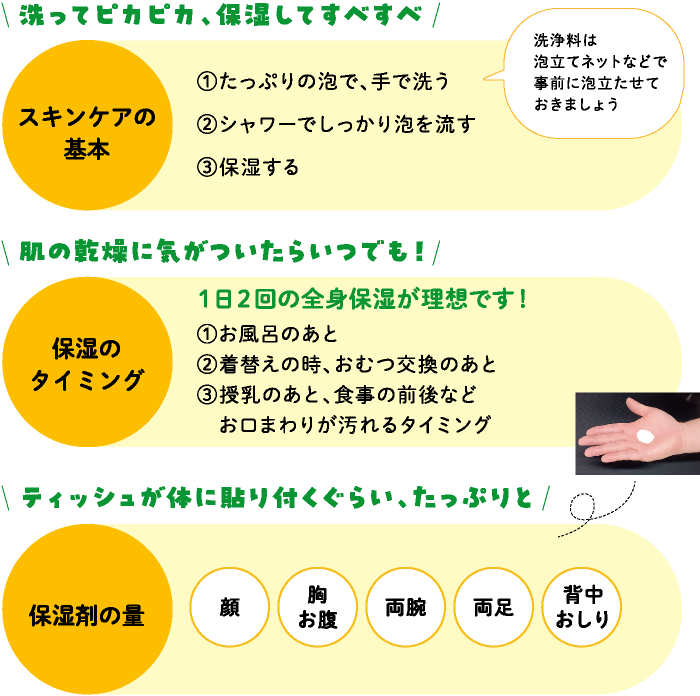
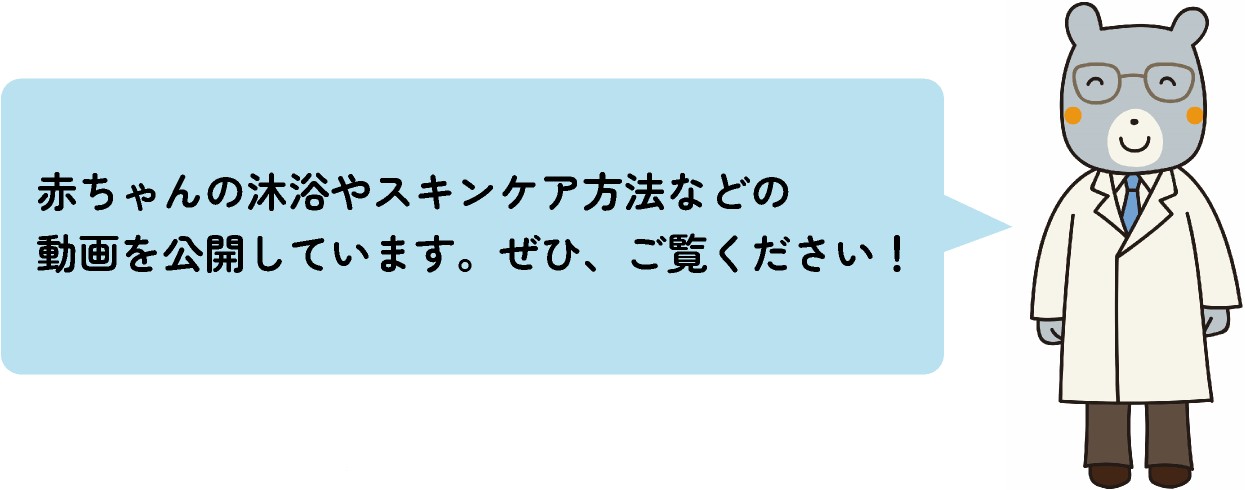

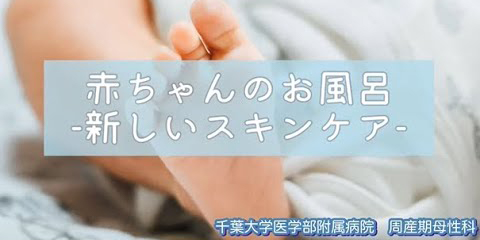
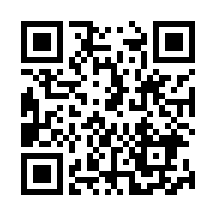
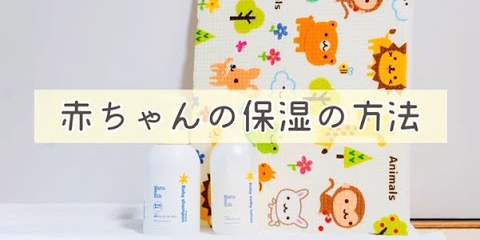
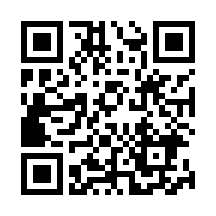
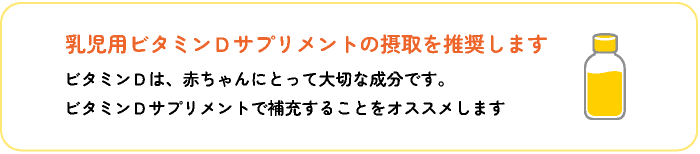
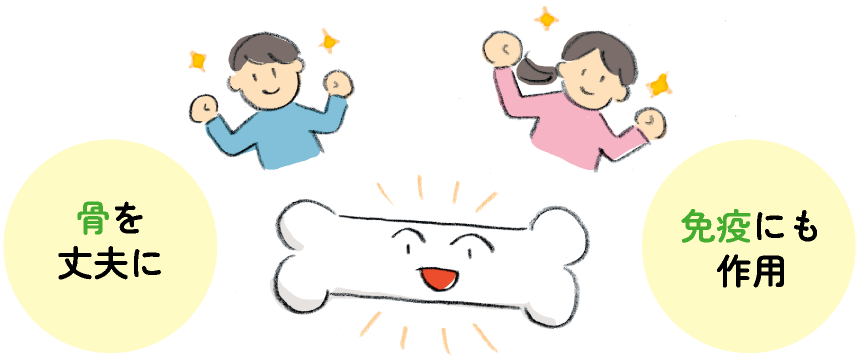
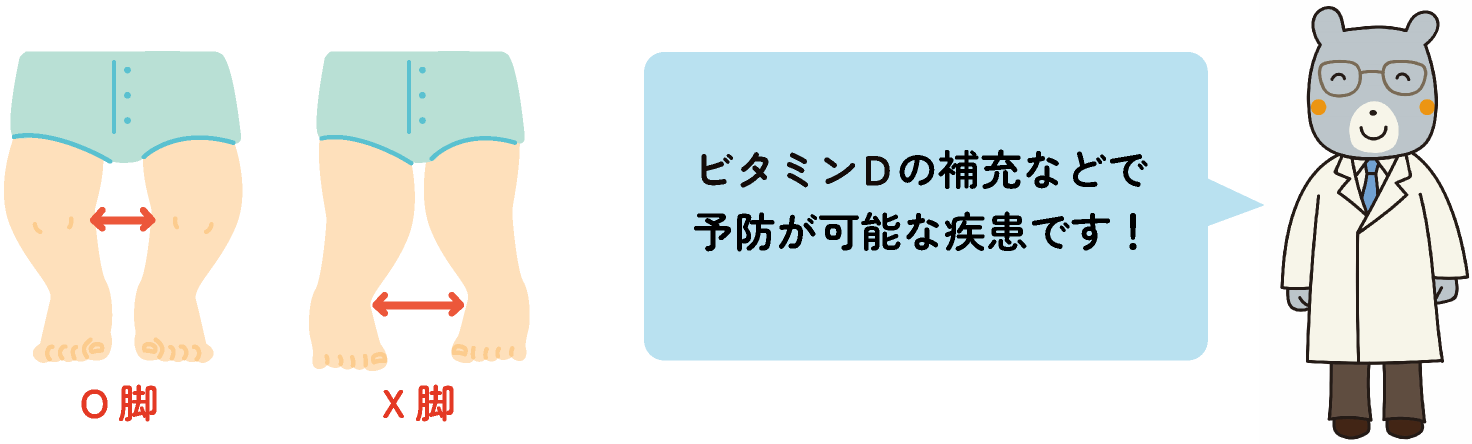

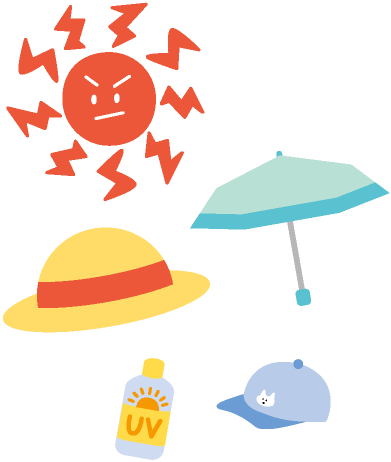

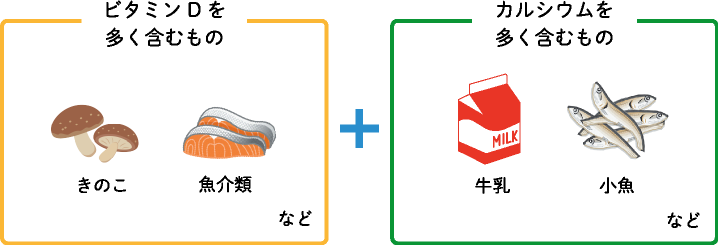
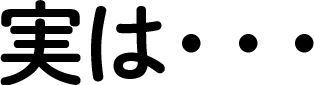
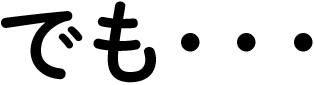

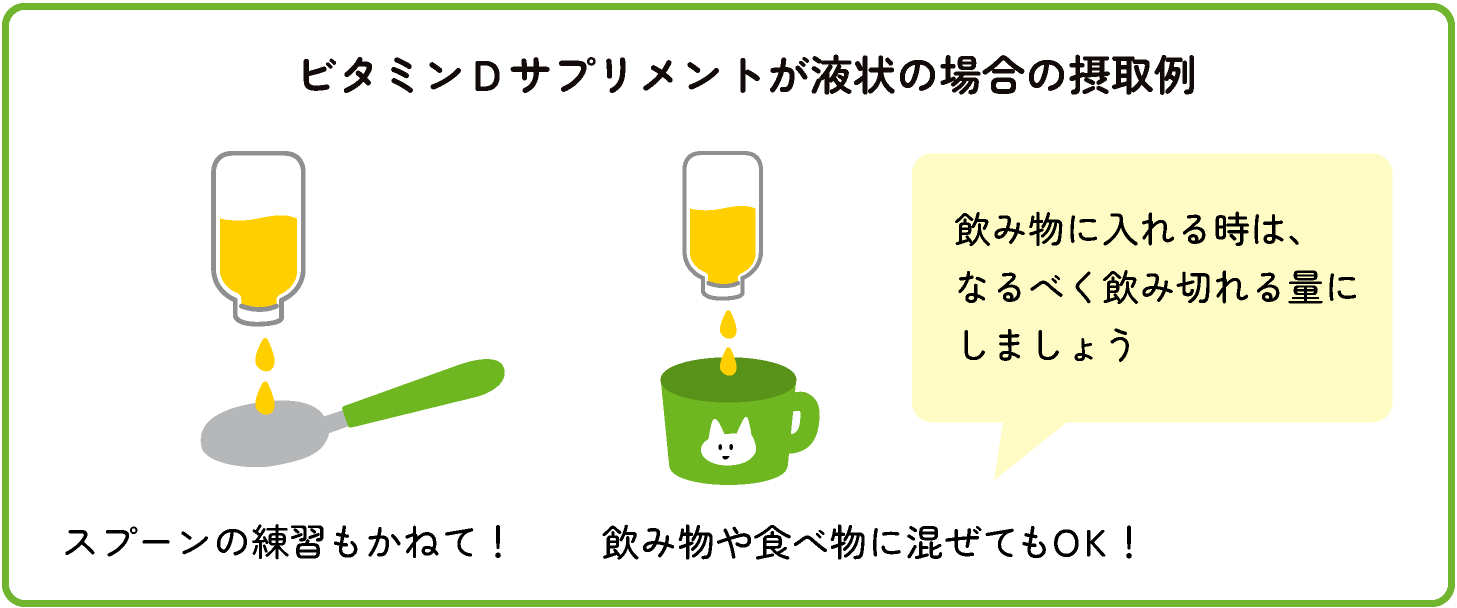
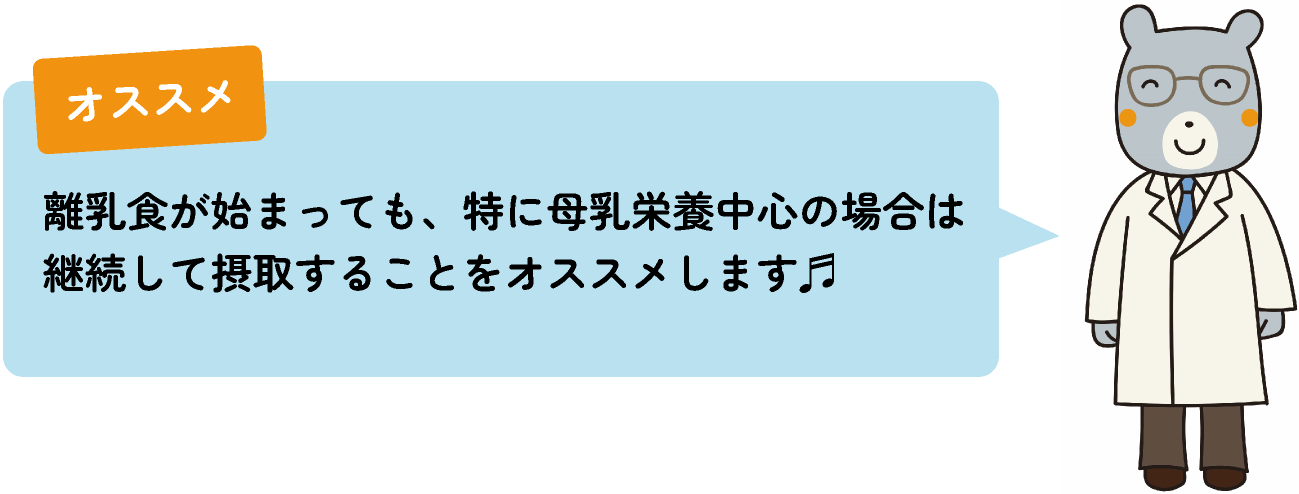
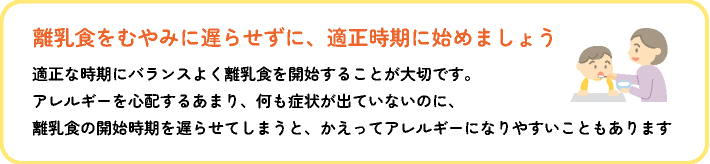
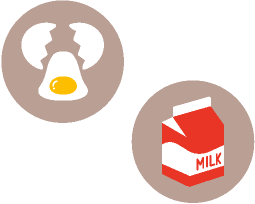
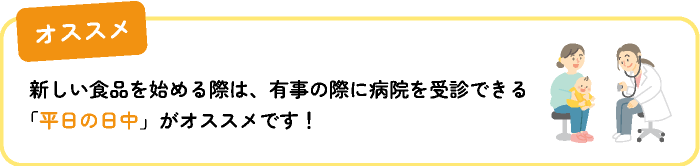
 食品の進め方(PDF形式、513KB)
食品の進め方(PDF形式、513KB)